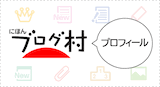リタイアして低所得者となり、健康保険料は7割軽減が適用されています。
2023年に支払った嫁と2人分の保険料は38,700円。
ただ、8カ月間、毎月約5,000円ぐらいをコンビニで支払いますが、支払い時にはこれでも高いなぁ・・・と感じてしまいます。
物を買う時とは違い、保険は目に見えない費用だからでしょうね。
7割減額のハードル
2024年も7割軽減を受けるには、Ranpaの場合は世帯の所得金額の合計が43万円以下という条件をクリアしなくてはなりません。
しかしこの条件は厳しく、確定申告で還付金を取るのか健康保険料の減額を取るかのどちらかを選択することとなってしまいます。
いろいろと試算をして、住民税非課税世帯、国民年金の全額免除についても同時に該当するよう、なるべく還付金を多くしながら健康保険料の7割軽減を目指すようにしました。
途中は5割減額でも良いかなぁ・・・とも考えたのですが。
7割、5割、2割の違い
7割減額、5割減額、2割減額を比べると、それほど大きい金額の違いとして感じないのかもしれません。
しかし、コンビニで実際に支払う時には、7割でも高いなぁ・・・と、思うぐらいですから、気分的な負担感の違いは大きいのだろうと思います。
5割減額となれば7割の1.66倍の保険料、2割軽減であれば2.66倍ですから。
同じサービスを受けるのに、今まで5,000円でよかったものが、5割減額となれば8,333円の支払いとなってしまいまいますので。
一物多価
とは言え、リタイアした今となっては、サラリーマンの時の健康保険料は60万円/年でしたので、あり得ないような価格設定であったなぁ・・・と感じます。
基本的に健康保険として受けるサービスは同じなのですが。
ましてやサラリーマンの時は忙しくて病院に行くことも少なかったと思います。
一物多価というのは知らなければそれで良いのですが、多価であることを知ってしまうと、急に損した気分になってしまうものですね。
興味がある方はこちらもどうぞ。。関連ブログ。
| にほんブログ村 セミリタイア生活 にほんブログ村 配当・配当金 にほんブログ村 FIRE |